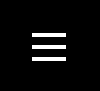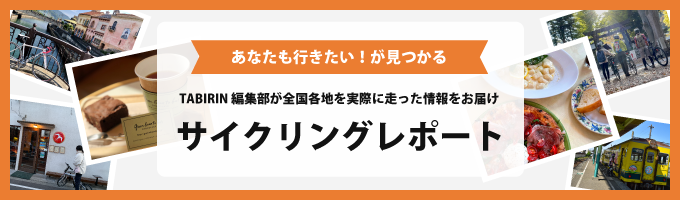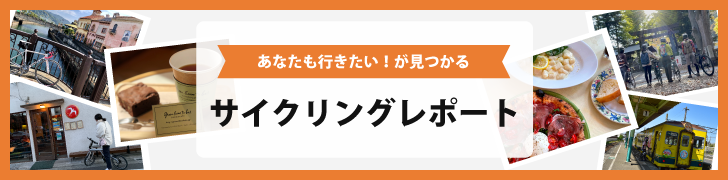「この日本の社会に思いはあるのか。そして思いを交換して生きていくことはできるのだろうか。」|自転車旅人・西川昌徳さんのdailylife stories#最終回


昨年6月からはじめたコーヒーを振舞いながら日本全国をまわる旅dailylife bicycle coffeeで、僕は無一文から東京でコーヒーを淹れはじめた。約1年、北海道から鹿児島までの7000kmを走りながら、毎日出会う方にコーヒーを淹れ、対話し、そしてときにお返しをいただきながら旅を続けさせていただいた。
目次
限りなく日常に近い、けれどもどこか違う旅
この旅が僕にもたらしてくれたものは何なのだろう。
鹿児島で今回のフリーコーヒーで日本をめぐる旅を終えて、自分の学校授業、講演活動に戻るなかで知人にあったり、この旅で出会った方々に挨拶に行きながらそんなことを聞かれ考えてみる。
この旅はこれまでのどんな旅とも違っていた。
知らない土地を走るのではなく、言葉も文化も違う世界に飛び込むのでもなく、走りながら出てくる道路標識は馴染んだものだったし、そこに出てくる地名も一度は聞いたことのあるものだった。それは限りなく日常に近い、けれどもどこか違う旅だったのだと思う。
もしかしたら旅には「スイッチ」のようなものがあるのかもしれない。
別の言い方をするならば「フィルター」みたいなもの。
そのスイッチが入ると、少し意識の持ち方が変わってくる。
そのフィルターを通して世界を見るとさっきとは違ったものが見えてくる。
もしかしたら今回の旅は、自分の知ってる土地なのに、自分の知らない世界を見せてくれた旅だったのかもしれない。




一杯のコーヒーを淹れるために、ぼくがやってきたこと
これまで僕は走っていた。走りながらその世界を見て、人と出会い、そして休むために立ち止まっていた。けれど今回は、自分が止まっている時間こそが目的だった。フリーコーヒーをはじめ、街の様子や、そこを行き交う人を見つめながら思いをめぐらせる。そして、僕のところに誰かが立ち止まってくれたところから、物語がはじまるのだ。
「コーヒー飲めるんですか?」
たいていはこの言葉からはじまる。もちろんズバッと目の前にやってきて一杯ください!と声をかけてくださる方もいる。けれどもどちらにも共通するのは、他人の空間に飛び込むことをしてくださっているということだ。そこから関係ははじまっていく。違う色をした2つの円が重なり合って、そこの色が濃くなったり変わったりしていくように。
一杯のコーヒーを淹れるために、ぼくがやってきたこと。
鉄瓶に水を注いで火にかける。
自分で焙煎した豆を銅のメジャースプーンですくって、古いイギリスのコーヒーミルに入れてハンドルをまわす。
水にさらしたコーヒーネルの水分をよく切ってハンドルに通して、ガラスでできたコーヒーサーバーの上に置く。
そこに中挽きぐらいに砕いたコーヒー豆をネルにいれて表面を整える。
鉄瓶の湯が湧いたらドリップポットにうつしかえて、やさしくコーヒー豆の上にお湯をのせて蒸らしをする。
膨らんだ豆の真ん中から、少しずつお湯をのせて泡を広げていきながら、そのきめ細かい泡のドームをくずさないように育てていく。
コーヒーを落としながら、そばちょこにお湯を注いであっためておいて、決まったラインまできたらハンドルを持って、ネルをうつしかえる。
コーヒーができたら、そばちょこの湯をポットに戻し、最後に注いで完成。
入ったコーヒーを目の前の人に手渡すときに、僕のなかではひとつが終わる。
それは相手の喜ぶ顔が見たい、美味しいと言ってもらいたい、という感覚とはちょっと違っていて、どちらかというとそう思ってもらえたらいいなと願いを込めるという感覚に似ている。そこから先の相手のリアクションはあくまでおまけみたいなものなのだ。僕は相手のリアクションを目的とするのではなく、自分のなすべきことを全うするというような気持ちでコーヒーを淹れた。
そのコーヒーを受けとるときに、なんだかぎこちないひとがいる、うれしそうな顔をするひとがいる、ときにはもうおいしい顔をしているひとだっている。だから不思議だ。コーヒーって味だけじゃなくて、そこにかかっている手間や時間が見えたときに、ひとつの世界となるような気がする。
きっと僕のコーヒーを飲みにきてくださったほとんどの人は、毎日どこかでコーヒーをコーヒーを飲んでおられるのだろう。けれど僕のコーヒーはとにかく時間がかかるし手間もかかるんだけれど、その時間こそがまた僕のコーヒーを飲みに来てくださった方と重なる。それは自動販売機でボタンを押しても、コンビニのコーヒーマシーンのボタンを押しても得られないもの。ひととひとだからこそ重なっていくもの。そしてその重なりは重くなったり、濃くなったりするのではなくて、どこか軽やかな気がする。
その僕のコーヒーを淹れる時間、そしてコーヒーを飲んでいただきながら生まれた対話は、その人のこころにふんわりとした余白を生み出したように思う。そして、その余白のようなものにはさまざまなものが溶けていく。僕の思いかもしれないし、その人が僕に思うことなのかもしれない。そこにはお互いの話も溶けていく、気づけば時間が経っていたということもたくさんあったし、涙を流しながら語りかけてくださった方もたくさんいた。そこには心の重なりがあったのだろうと今なら思う。











余白さえあれば、誰かがそこに入ってくる
僕はこのコーヒーの旅をする前に、ひとつの世界を思い浮かべた。
心通わせることができる、思いが循環する社会であってほしい。
そのためにコーヒーを淹れはじめた。
旅のはじめ無一文であることから来る不安に負けそうになった。とにかく一生懸命にコーヒーを淹れ続けた。そのうちに信じられるようになった。「自分の思いがこもったコーヒーはきっと誰かに届き、そしてなんらかのカタチになって帰ってくる」と。それからは自分の心に余白が生まれたように思う。
思いを確かめるために、通わせるために一生懸命にならなくていいのだ。
それはまるで正反対のことを言っているように思われるかもしれない。
けれど自分にその余白さえあれば、誰かがそこに入ってくることができる。違うひとが目の前にいたならば、その余白で受け止めることができる。
余白があるからこそ重なりあえるのだ。
そしてその余白は、自分から生まれただけでなく、誰かの優しさがもたらしてくれるものでもある。
自分が心にゆったりとした空間を持って、街に立つようになったとき。
不思議だけれど、流れていくような感覚があった、それは出来事だったり、出会いだったり。
自分でどこかを目指して泳いでいくのが人生のようなものだと思っていたとしたら、それとは違って、川の流れをぜんたいで見ながらうまく流れのポイントを見つけて、そこに身を寄せていくと人生が流れはじめた。そんな感覚だ。そしてそうして流れていく先には、自分にとって必然としか思えないような出来事や出会いが待っていたのだ。
これはスピリチュアルでもなんでもなくて、余白が持つ可能性なんだと思う。
ひとりでつくりあげられるものの可能性を、誰かとつながりあうことでつくりあげられるものの可能性がうわまわるということなんだと思う。だからこそ、ひとにも、社会にもその余白が必要なのかもしれないと感じた。
社会であっても、人の人生であっても不安は必ず生まれる。
けれどルールや縛り、見通しを立てることによってその不安をぜんぶ摘みとるのではなく、その不安や課題を見つめながらも歩むことができるだけの余白を持っていたなら、そこからまたなにかが生まれていくんだとぼくは信じる。
このフリーコーヒーの旅は限りなく日常に近く、けれども僕に新たな世界を見せてくれたと思う。そして、旅が終わっても僕はまだコーヒーの香りが部屋にとどまるように、その旅の余韻を持ちながら新たな日常を生きている。人生は旅だというけれど、この旅でもう少し僕の日常は旅に近づいているような気がしている。
旅するように生きること。この言葉と余白を心にもって、新たな旅に出ようと思う。


























今回のフリーコーヒーの旅で出会えたすべてのかたに、そしてこのコラムを読んでくださったかたに心からの感謝を込めて。
ありがとうございました。

(おわり)
(執筆:西川昌徳)
<<#9 「夢物語への挑戦 フリーでコーヒーを淹れる理由」へ
プロフィール

西川 昌徳(にしかわ まさのり)さん
Masanori Nishikawa
自転車旅人
1983年兵庫県姫路市出身 徳島大学工学部機械工学科卒業
世界36カ国90,000km。世界中を自転車で旅する中で生まれた思いや学び、気づき、出会いの物語を伝える旅人。旅先と日本の学校をテレビ電話でつなぐ課外授業「ちきゅうの教科書」を実施するほか、日本各地で講演会を実施。地球上で最も活躍した冒険家、挑戦者、社会貢献活動を表彰するFAUST A.G. AWARDS 2014 ファウスト社会貢献活動受賞。
>>EARTH RIDE – MASANORI NISHIKAWA official website